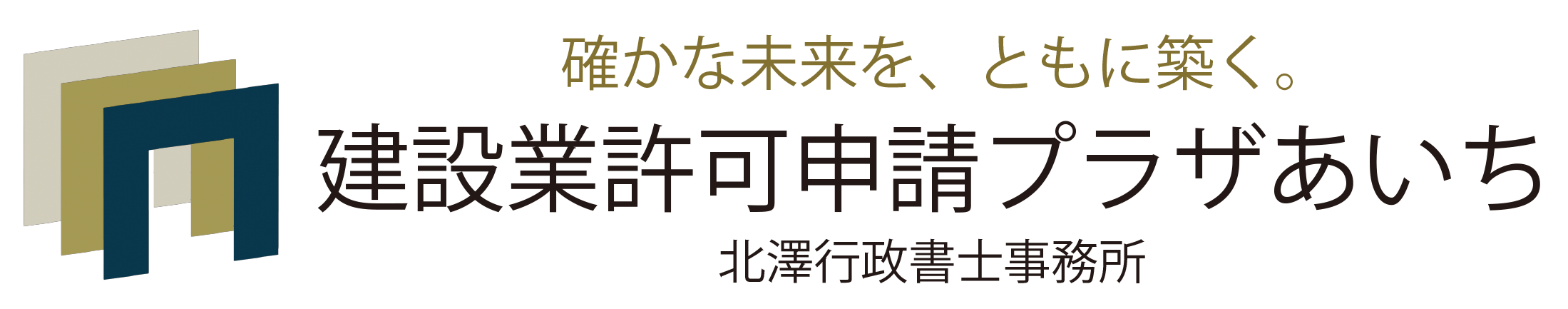建設業の許可申請は、初めての方にとっては複雑でわかりづらいもの。 このページでは、許可が必要となるケースや29業種の違い、知事許可と大臣許可の区分、そして一般・特定の許可の違いまで、建設業許可の基礎知識をわかりやすく整理しています。 「自分はどの許可が必要なのか?」と迷ったときの道しるべとして、ぜひご活用ください。

建設業許可の基礎知識
目次
[1.建設業とは]
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる29業種にわかれています。
土木工事・建築工事・大工工事業・左官工事業・左官工事業・石工事業・屋根工事業・電気工事業・管工事業・タイル・レンガ・ブロック工事業・鋼構造物工事業・鉄筋工事業舗装工事業・舗装工事業・しゅんせつ工事業・板金工事業・ガラス工事業・塗装工事業・防水工事業・内装仕上工事業・機械器具設置工事業・熱絶縁工事業・電気通信工事業・造園工事業・さく井工事業・建具工事業・水道施設工事業・消防施設工事業・清掃施設工事業・解体工事業

許可を必要とする方
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、次の『許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)』を除きます。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
| 建築一式工事 | 下記のいずれかに該当する場合 ⑴1件の請負代金が1,500万円(消費税含む)未満の工事 ⑵請負代金額に関わらず木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事 |
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 |
請負代金の額は、同一の建設業を営む方が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額となります。「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものです。「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
[2.許可の種類]
知事許可と大臣許可
1つの県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事の許可が必要です。

1つの都道府県のみに営業所
県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。

2つの都道府県に営業所
営業所とは・・・
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。
なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。
一般と特定の建設業許可
1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
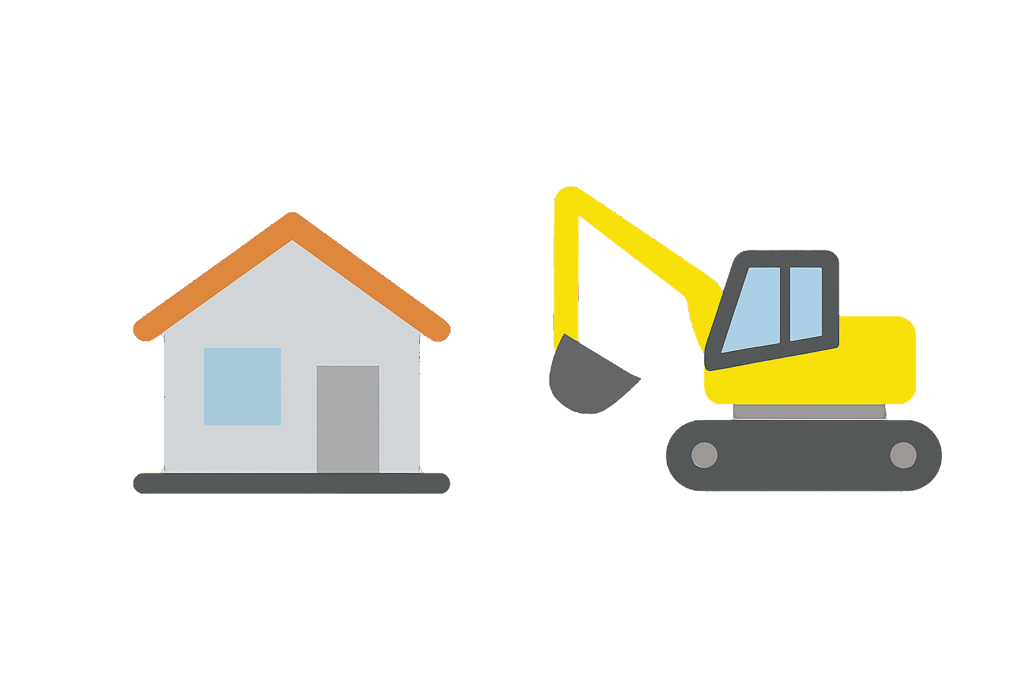
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
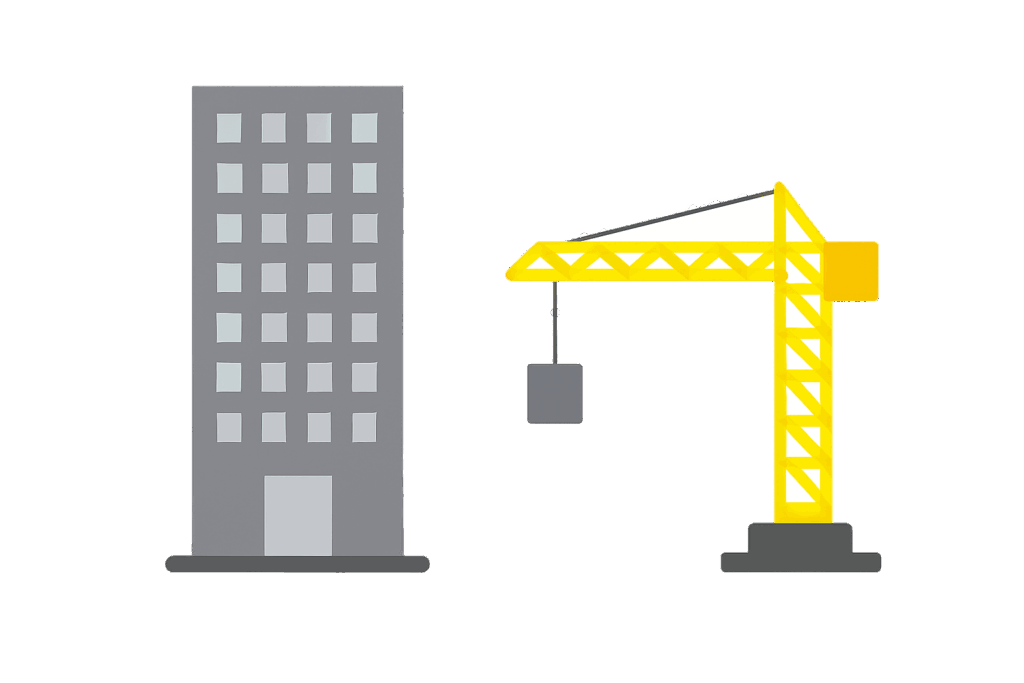
附帯工事について 許可を受けて建設業を営む方は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)も請け負うことができます。この附帯工事とは、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものです。附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します。
[3.許可の要件]
愛知県で建設業の許可を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。また、特定建設業の許可を受けるには、一般建設業より要件が重くなります。
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
⑴適正な経営体制を有していること
次のいずれかに該当するものであること。
イ.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
⑵適正な社会保険に加入していること(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)
次のいずれにも該当する者であること。
健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。


2.専任技術者
営業所ごとに下表のいずれかに該当する専任の技術者がいること
許可を受けようとする業種の工事について
・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
・学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の所定学科卒業後又は同法による専門職大学の前期課程の所定学科修了後3年以上の実務経験のある方
10年以上の実務経験を有する方
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方
(二級建築士、二級土木施工管理技士等)
許可を受けようとする業種の工事について
国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
※指定建設業については、イ又はハの規定で国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限る
3.誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな方でないこと
・法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合)が該当対象者となります。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が、 建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合
4.財産的基礎等
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
下記のいずれかに該当すること
申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力のあること
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
申請日の直前の決算において、下記の要件すべてに該当すること
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
〈一般建設業の財産的基礎又は金銭的信用〉
前表の「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。個人事業で事業開始後決算期未到来の場合は500万円以上の預金残高証明書」が必要となります。
前表の「資金調達能力」については金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前4週間以内のもの)もしくは「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前4週間以内のもの)により判断します。なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。
〈特定建設業の財産的基礎〉
申請日の直前の決算において、前表の要件すべてを満たさなければなりません。
※ なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます
[4.欠格要件]
申請者の方が次の1から14まで(許可の更新を受けようとする申請者の方は、1又は7から14まで)のいずれかに該当する場合は、許可は受けられません。
また、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
2.建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第75号又は第86号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
3.法第29条第1項第75号又は第86号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方
4.3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前60 日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方
5.法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
6.許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方
7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
8.法、又は一定の法令の規定(※)により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同
10.精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
11.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から10まで又は12(法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する方
12.法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方
13.個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその方が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった方を除く。)のある方
14.暴力団員等がその事業活動を支配する方