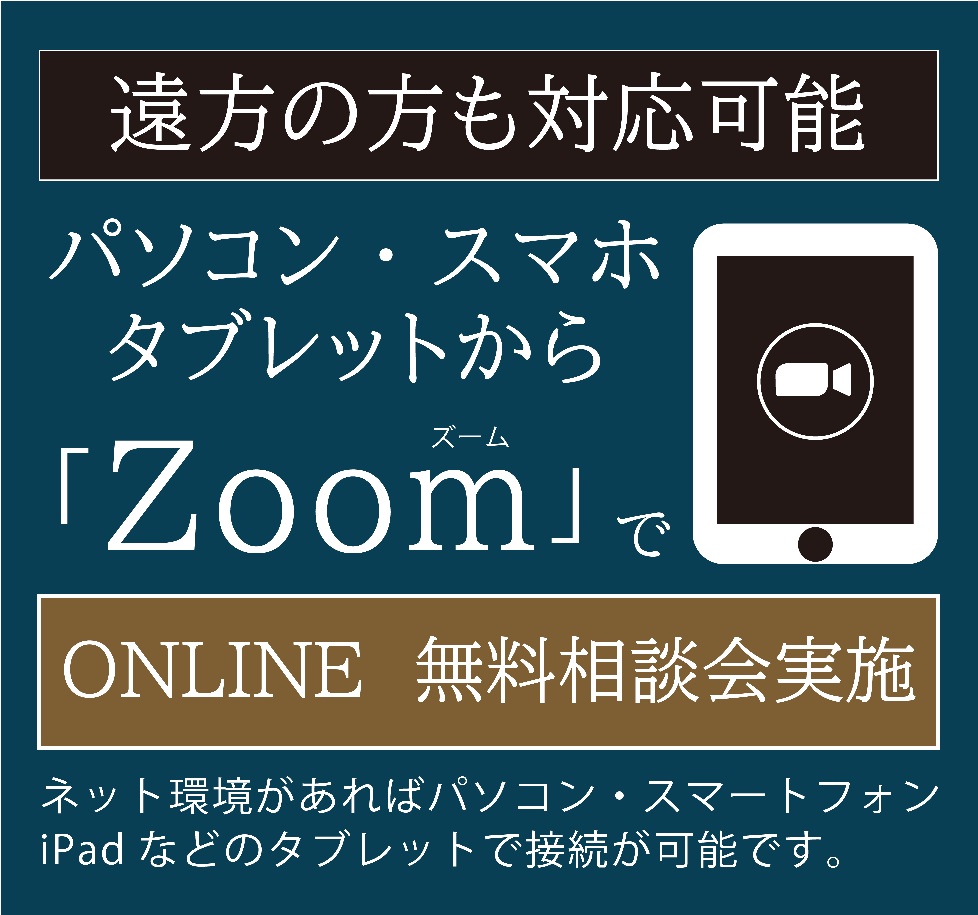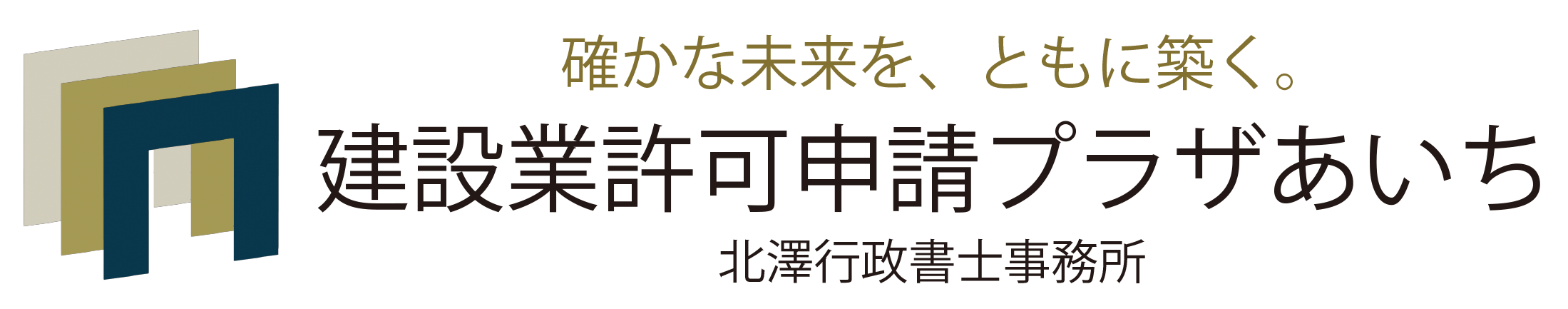建設業許可申請プラザあいちは、初めての許可申請も、更新手続、変更手続きなど、建設業を営む上での“面倒”を、専門家がわかりやすくサポートします。個人事業主から法人まで、愛知・岐阜・三重を中心に、迅速・丁寧な許可取得を専門行政書士が直接対応し、安心のサポート体制を整えています。
新規取得者向けに、要件確認から申請書類作成・提出まで丁寧にサポートします。
商号・役員・営業所などの変更届や、5年毎の更新申請を確実にサポート致します。
新たな工事業種の追加申請を技術者要件の確認から提出まで一括でお手伝いします。
毎年の決算報告や経営事項審査の申請を書類作成から提出まで一貫して支援します。
こんなお困りごとはございませんか?

取引先から「許可業者でないと契約できない」と言われた

経営業務の管理責任者って誰が該当するの?

過去の工事実績をどうやって証明すればいい?
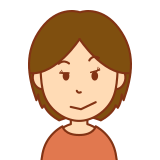
書類の書き方がわからず、役所から何度も修正を求められた
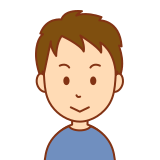
公共工事に参加したいが、許可が必要だった
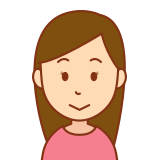
技術者の資格や経験年数が足りているか不安
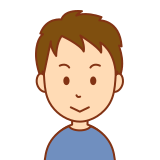
経営業務の管理責任者の要件が複雑すぎて理解できない

許可は取れたけど、更新のタイミングが分からない
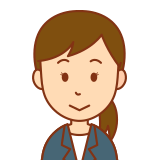
そもそも自社が許可を取れるのか分からない
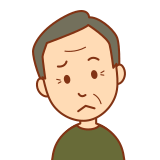
法人ではなく個人事業でも建設業許可は取れるの?
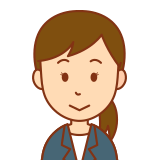
技術者の資格証明や実務経験の書類が揃わない
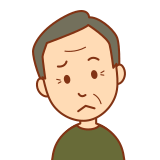
代表者が交代したり、技術者が退職したらどうする?
そんなお悩みは「建設業許可申請プラザあいち」にお任せください!
愛知県で建設業許可の取得から、書類作成・役所対応・取得後のフォローまで 専門スタッフが一つひとつ丁寧にサポートいたします。 「うちでも許可が取れるの?」というご相談からでも大歓迎です。 まずはお気軽にご相談ください。
当事務所の強み
許可取得まで完全サポート
経験豊富な行政書士が、書類作成から提出まで一貫して対応。また許可取得後の更新・変更・毎年の事業年度終了届も継続して支援します。

地元密着・迅速対応
名古屋市を中心に、愛知県全域に対応。現地調査や面談もスピーディに実施。「急ぎで許可を取りたい」「直接相談したい」等のニーズにも柔軟に対応可能。

豊富な実績と専門知識
当事務所には一級建築士が在籍しており、建設業許可に特化したサポート実績多数。実務経験や資格など各工事業種の複雑な要件も丁寧に解説します。

補助金申請に強み
当事務所は創業向けや新事業展開時に対応する補助金申請サポートの実績が多数。許可取得を機に事業拡大を図る際に、資金調達をサポートします。
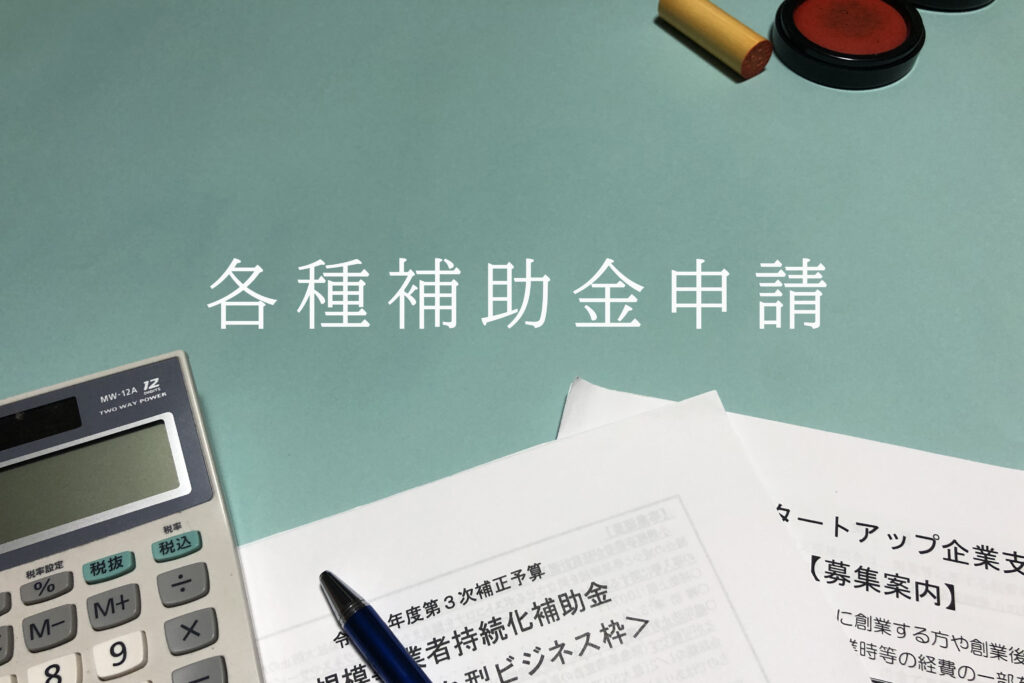
建設業許可について
[建設業とは]
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる29業種にわかれています。
1.土木工事業
2.建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業

7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業

10.タイル・レンガ・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業

19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業

28.清掃施設工事業
29.解体工事業
許可を必要とする方
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、次の『許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)』を除きます。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
| 建築一式工事 | 下記のいずれかに該当する場合 ⑴1件の請負代金が1,500万円(消費税含む)未満の工事 ⑵請負代金額に関わらず木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事 |
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 |
[許可の種類]
知事許可と大臣許可
1つの県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事の許可が必要です。
県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
一般と特定の建設業許可
1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
[許可の要件]
愛知県で建設業の許可を受けるには、主に以下の5つの要件を満たさなければなりません。
経営業務の管理責任者

建設業の経営を適切に管理できる経験者が、常勤役員等として在籍していることが必要です。原則として、過去5年以上の経営経験が求められます。
営業所技術者
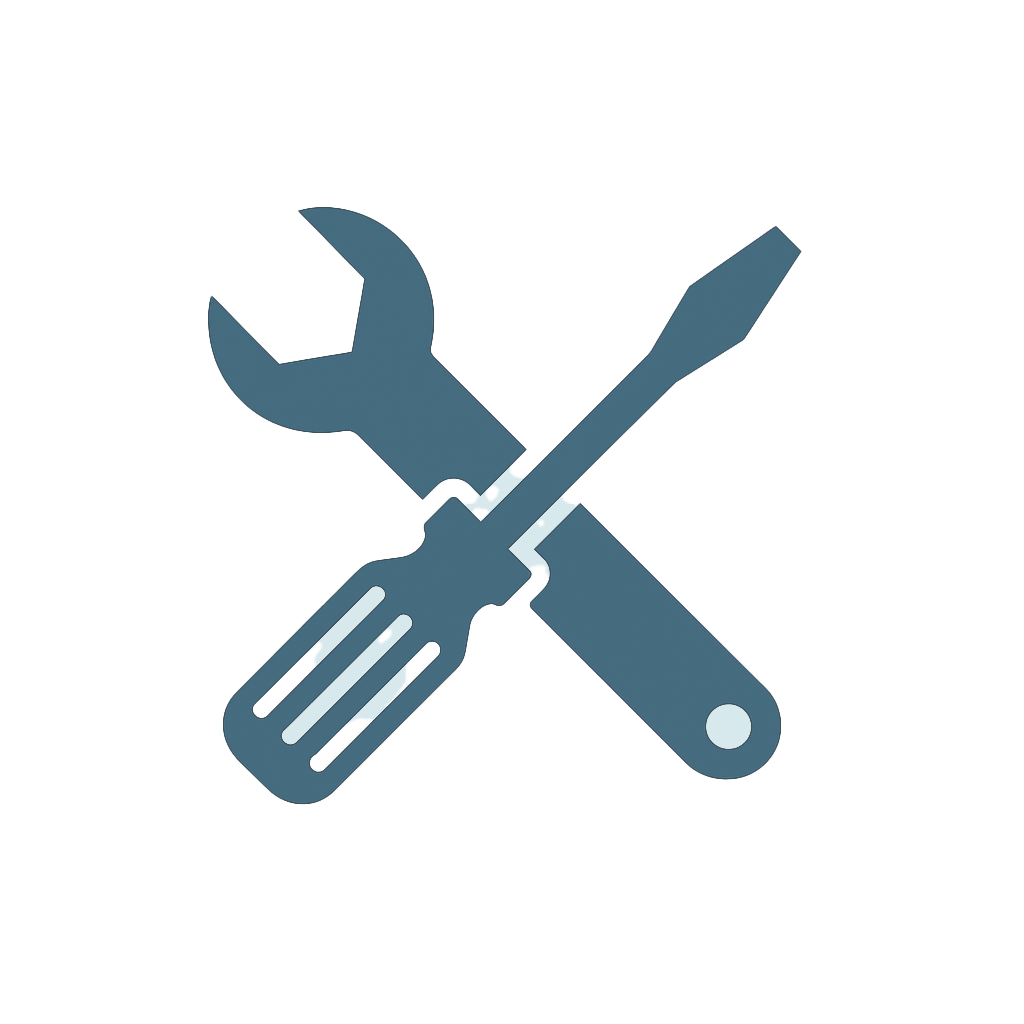
営業所ごとに、許可を受けたい業種に関する資格や実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。一定年数の実務経験で認定されることがあります。
誠実性

請負契約に関して、不正や不誠実な行為を行う恐れがないことが求められます。過去に法令違反等を受けた場合は、許可が認められないことがあります。
財産的基礎

契約を履行するために十分な資金力や信用があることが必要です。一般建設業では自己資本500万円以上、または同等の資金調達能力が求められます。
欠格要件非該当
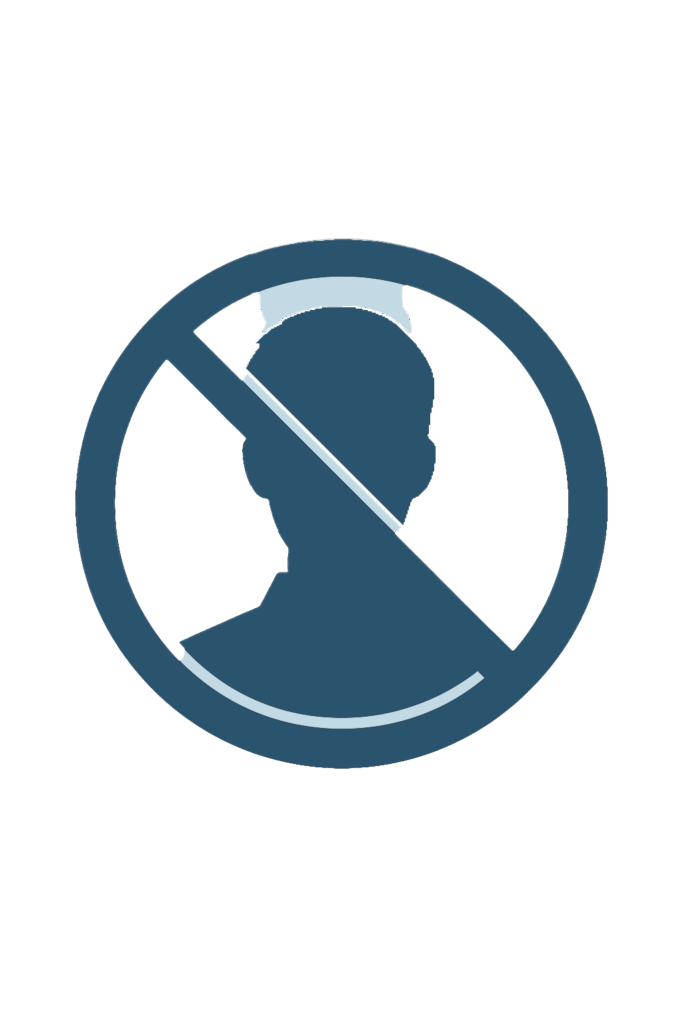
破産手続中や禁錮以上の刑を受けた直後など、一定の法令違反歴がある場合は許可を受けられません。申請者本人だけでなく、役員等も対象となります。
申請までの流れ
- STEP1お問合せ(無料相談)
建設業許可に関するお悩みやご不安は、専門の行政書士が直接お伺いします。 初回のご相談は無料ですので、お問合せフォームまたはお電話にてまずはお気軽にお問い合わせください。

- STEP2ヒアリング・事前確認
ご希望の業種や事業内容、現在の状況を詳しくお聞きし、許可要件の確認を行います。 欠格要件や必要書類についても丁寧にご説明いたします。

- STEP3お見積書の提示・サポート契約締結
ヒアリング内容をもとに、必要な手続きや書類作成の範囲を明確にしたうえで、正式なお見積書を提示いたします。 ご納得いただけましたら、サポート契約を締結し、申請準備を本格的に開始いたします。 費用やスケジュールについても丁寧にご説明いたしますので、安心してご依頼いただけます。

- STEP4書類の収集・作成
必要な書類の収集をサポートし、申請書類を正確に作成します。 経営業務管理責任者や専任技術者の要件確認も含め、専門的な視点で対応します。また提出する税務や謄本等の書類の取得も代行します。
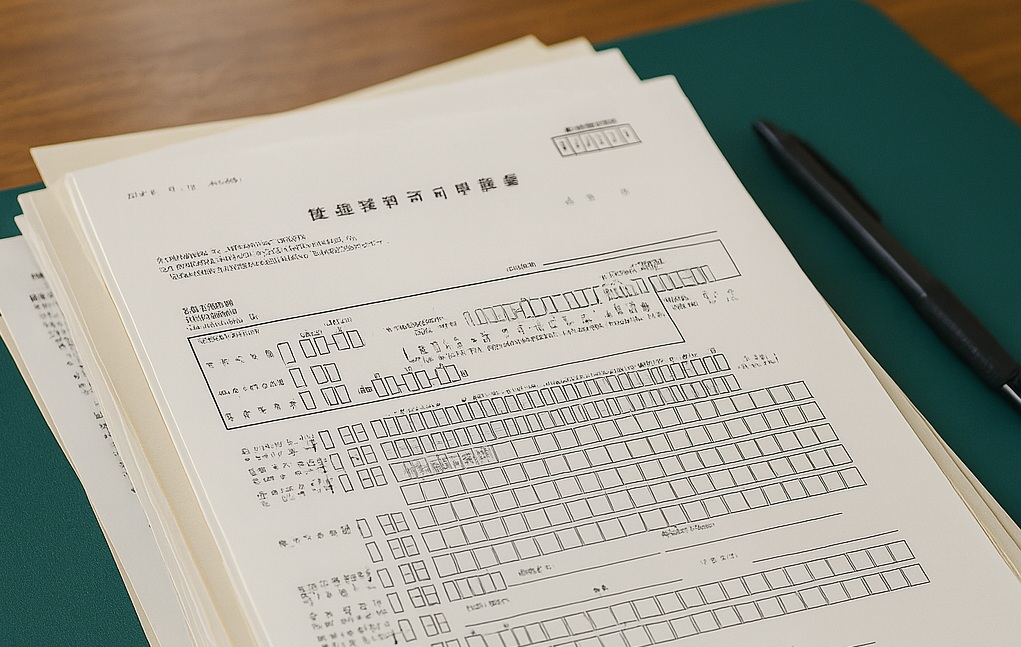
- STEP5申請手続き(提出代行)
書類が整い次第、管轄の行政庁へ申請を行います。 必要に応じて、申請窓口の担当者と事前に打合せを行い、申請内容の確認や見通しについて調整を行います。 こうした事前確認により、申請後のトラブルや補正のリスクを最小限に抑えることができます。 申請は当事務所が責任を持って代行し、進捗状況も随時ご報告いたします。

- STEP6建設業許可通知書の送付
提出先の行政庁の審査を経て、晴れて建設業許可となり、知事等発行の「建設業許可通知書」がお客様宛に届きます。今後の手続きや注意点についてもご説明します。 更新や変更届など、取得後のサポートも継続して行います。
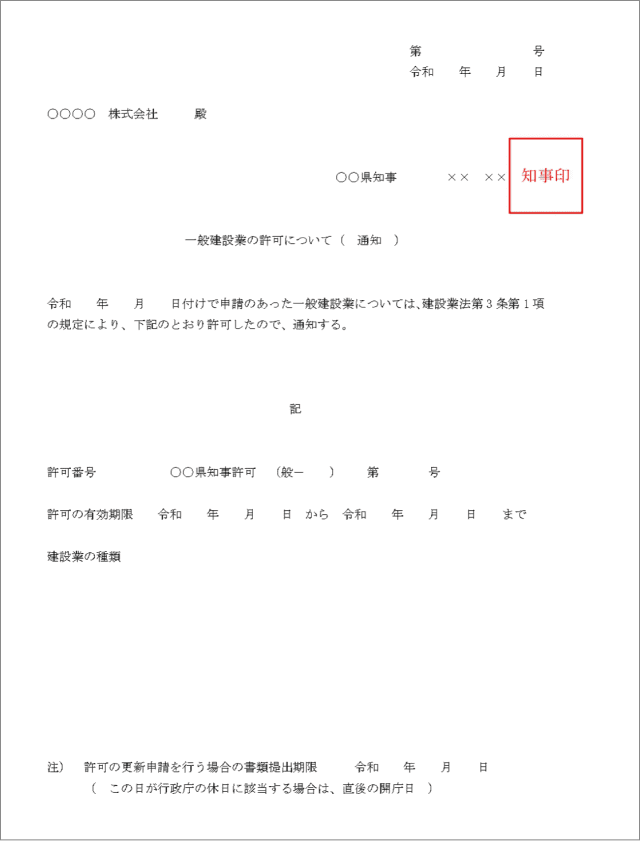
行政書士に建設業許可申請の代行を依頼するメリット
許可取得のカギは“正確な準備”と“的確な判断”。 建設業許可に精通した行政書士が、あなたの状況に合わせて最短ルートをご案内します。
複雑な要件を的確に整理できる

建設業許可は、業種ごとの技術者要件や経営業務管理責任者の確認、財務状況の証明など、専門的な判断が求められます。行政書士は法令と実務に精通しており、申請者の状況に応じて必要書類を的確に整理し、無駄なく準備を進めることができます。
書類不備による申請遅延を防げる

申請書類は細かな記載ミスや添付漏れでも受理されないことがあります。知識が豊富な行政書士に依頼すれば、書類の精度が高まり、窓口での指摘や再提出のリスクを大幅に減らすことができます。結果として、許可取得までの時間も短縮されます。
審査官とのやり取りもスムーズに

行政書士は、管轄の建設事務所とのやり取りにも慣れており、補足説明や追加資料の提出にも迅速に対応できます。申請者が直接対応するよりも、専門家を通すことで審査官とのコミュニケーションが円滑になり、安心して申請を進められます。
専門性・正確性・安心感の3つが行政書士に依頼する大きなメリットです
よくある質問

- Q建設業許可は必ず必要ですか?
- A
請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を行う場合は、許可が必要です。軽微な工事のみを行う場合は不要なケースもあります。
- Q一般建設業と特定建設業の違いは?
- A
下請けに出す金額が一定額を超える場合は「特定建設業許可」が必要です。元請として大規模工事を行う場合に該当します。
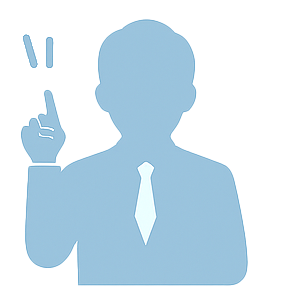
- Q個人事業で許可を取得していましたが、法人化しました。許可は引き継げますか?
- A
個人事業の法人化(いわゆる「法人成り」)は個人事業主(被承継者)と法人(承継者)との間での事業譲渡となり、一定の要件を満たせば、許可番号の継承が認められます。
- Q資本金が500万円未満ですが、許可は取れますか?
- A
自己資本が500万円以上あるか、預金残高で証明できれば可能です。複数口座の合算も認められますが、証明書の日付が揃っている必要があります

- Q専任技術者に資格がない場合はどうすれば?
- A
資格がなくても、10年以上の実務経験があれば認定される場合があります。ただし、単なる作業員経験は認められないこともあるため、証明書類の整備が重要です
- Q親が個人で許可を持っていましたが、亡くなりました。子が事業を継げますか?
- A
被相続人死亡後30日以内に申請を行うことで認可を受けられる場合があります。当然ながら承継者(相続人)が経管や技術者など、許可の要件を満たしている必要があります。

- Q許可取得後に社会保険に未加入だとどうなりますか?
- A
健康保険・厚生年金・雇用保険の適用事業所である場合は、届出が義務です。未提出だと許可取消の対象になることがありますので注意が必要です。
- Q許可を受けた営業所を移転した場合、どうすれば?
- A
営業所の所在地変更は、変更届の提出が必要です。提出を怠ると、更新時に不備となる可能性があります。
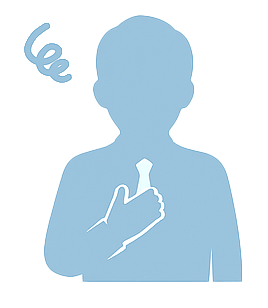
- Q許可を持つ法人の代表者が辞任しました。許可はどうなりますか?
- A
建設業許可は法人に帰属するため、代表者が辞任しても許可自体は継続されます。 ただし、経営業務管理責任者や専任技術者が退職した場合は、許可要件を満たす方を速やかに補充する必要があります。 これらの要件が欠けたまま放置すると、許可の維持ができなくなる可能性がありますので、早めの対応が重要です。
- Q許可の更新直前に自己資本が4,000万円未満になりました。特定建設業の更新は可能?
- A
特定建設業の更新には資本金2,000万円以上かつ4,000万円以上の自己資本が必要です。直前の決算期の財務諸表では資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準をクリアできる場合がございます。満たさない場合は更新できない可能性があります
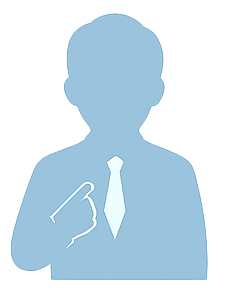
- Q工事経歴書に記載する技術者が退職してしまいました。どうすれば?
- A
実際に配置された技術者を記載する必要があります。退職後でも、当時の配置状況を証明できれば記載可能です
- Q許可取得までの期間はどれくらい?
- A
書類が整っていれば、申請から許可取得まで約1〜2か月が目安です。事前確認や補正が入ると延びることもあります。
- Q建設業許可の申請費用はどれくらい?
- A
行政手数料は約9万円前後。専門家である行政書士に依頼する場合は別途報酬がかかりますが、書類不備による再申請リスクを減らせます。
実績紹介
電気工事業
個人事業主・名古屋市

名古屋市で電気工事を営む個人事業主のA様は、許可取得に必要な「実務経験の証明」に不安を抱えていました。日々の業務に追われ、書類作成にも苦手意識が…。当事務所では、過去の契約書や請求書を丁寧に整理し、経験年数を裏付ける資料を一緒に構築。結果、申請から約1.5カ月で許可取得。 「自分ひとりでは絶対に無理だった」と、今では同業者にも紹介してくださっています。
内装仕上工事業
法人・刈谷市
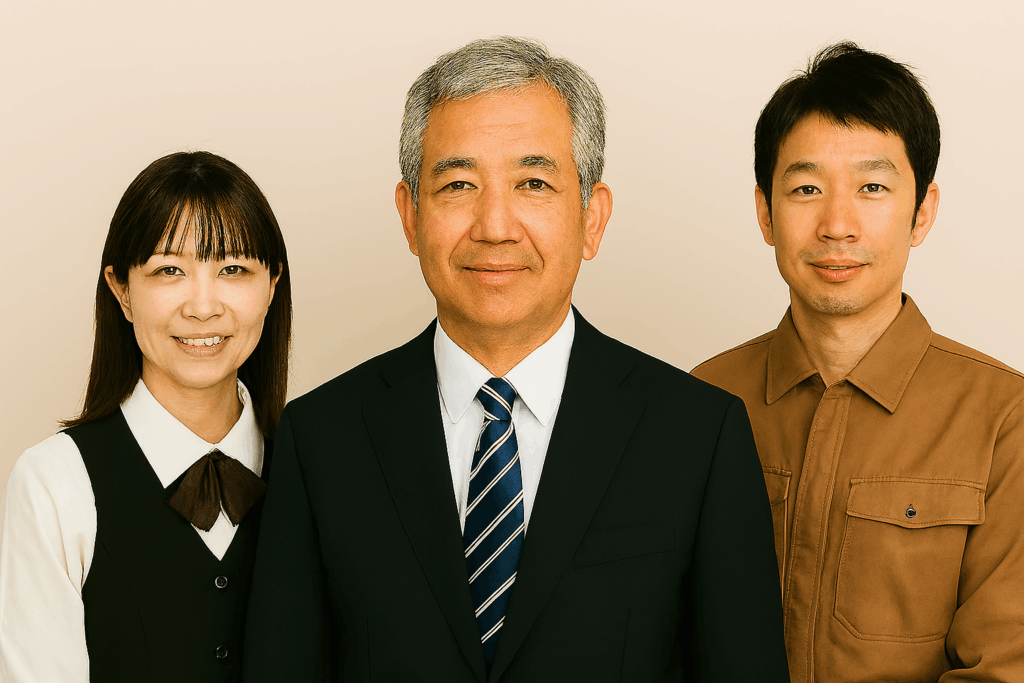
愛知県刈谷市のB社様は、5年来の取引先である元請企業から「半年後の大型案件に合わせて許可を取ってほしい」と急な依頼を受け、焦ってご相談に。ヒアリング後すぐに要件を確認し、必要書類をリスト化。社内での役割分担もサポートしながら、最短ルートで申請を完了。 「スピードと正確さに驚きました。助かりました!」と感謝の声をいただきました。
お問合せはこちらのフォームから
☎ 052-761-9430
Zoomを活用したオンライン相談会を実施しております。 建設業許可申請に関するお悩みやご不明点を、事務所にお越しいただくことなく、ご自宅や職場から気軽にご相談いただけます。 初回のご相談は無料で、事前にご予約いただければ、平日9:00〜18:00の間で柔軟に対応可能です。(時間外対応も可能)
オンライン相談をご希望の方は、お問い合せフォームより「Zoom相談希望」とご記入のうえ、ご希望日時をお知らせください。