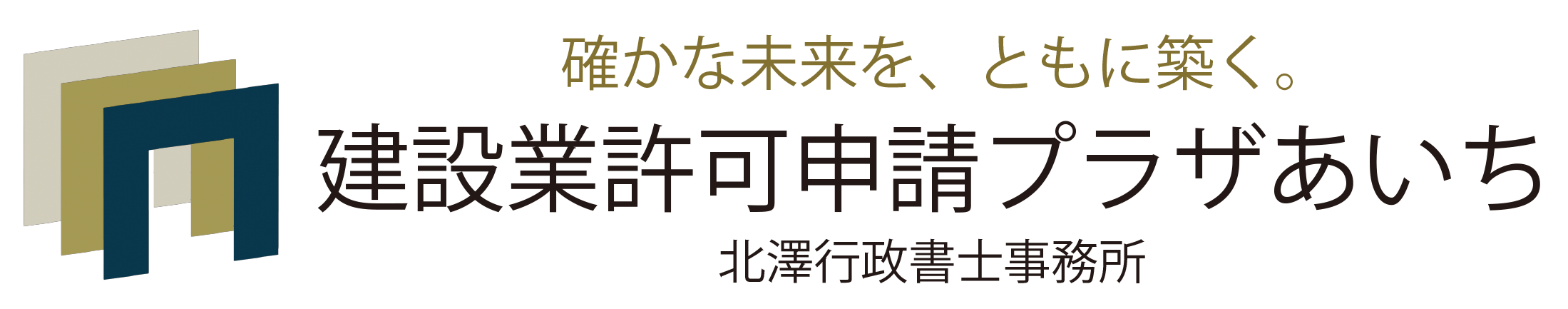建設業許可を取得するには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。中でも「経営業務の管理責任者」と「営業所の専任技術者」に関する条件は、申請の成否を左右する大切なポイントです。このページでは、建設業許可を受けるための要件について、具体的かつ分かりやすく解説します。初めての方でも安心して読み進められるよう、実務経験に基づいた視点でご案内いたします。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは?
建設業許可を取得するには、会社や事業所の経営を安定的に運営できる体制が求められます。その中核を担うのが「経営業務の管理責任者(通称:経管)」です。 これは、建設業の経営に実務経験を持ち、予算管理や契約締結などの意思決定を行ってきた責任者のこと。法人の場合は常勤役員、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。 国や自治体は、この人物が実際に経営を管理していたかどうかを確認することで、事業の継続性と信頼性を判断します。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
⑴適正な経営体制を有していること
次のいずれかに該当するものであること。
イ.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
<経営業務の管理責任者としての経験内容の確認・証明書類>
個人事業主の場合は、確定申告書+所得証明書を必要年数分
法人の場合は、証明期間中の必要年数において法人の目的および継続して役員であったことが確認できる登記事項証明書
個人・法人ともに①契約書、②注文書・注文請書、③請求書・入金確認資料(通帳や預金取引明細票)
上記の資料等で許可を受けたい業種の請負確認を証明します。
審査上のポイント
⑴工事の内容が確認できるか 現場名のみ記載されているなど、工事内容が確認できないものは資料として使用できません。見積書等、工事内容が確認できる資料が別にある場合は、それも添付が必要です。なお、一般的な工事名称でないなど、判断がつかない場合、内容の説明を求められる場合があります。
⑵建設業の業種が確認できるか 「修繕工事」や「改修工事」とのみ記載されているなど、工事であることしかわからない場合、見積書等、内容がわかる資料の添付が必要です。業種が特定できる記載内容であるか、ご確認ください。
⑶建設工事の請負であることが確認できるか 建設業の経営経験は、建設工事の完成を請け負った経験である必要があります。いわゆる「人工出し」や「応援」などの常用工事や、建設資材の販売の実績は、建設業の経営経験にはなりません。
請負工事の実績であるかは、書面上で確認できる必要があります。書面上、人工代しか計上されていない場合(常用工事の実績に見える)や、資材代のみ計上されていて工賃が表示されていない場合(資材販売の実績に見える)等は、それだけでは請負工事の実績としてみることができません。
⑷請求書等の金額と入金を確認する書類の金額が一致するか(③で確認する場合)
口座振込手数料や安全管理費等により、請求書の金額と実際の入金額が異なる場合、その内訳を確認する必要があります。特に、安全管理費などの差額が大きなものについては、その金額が分かる資料などにより説明を求められる場合があります。
⑸浄化槽工事業登録、登録電気工事業、解体登録を受けた業者における請負実績確認について
個人事業主にあっては、確定申告書において、その職業欄に当該業種に係る職業である記載の確認ができ、かつ、年間を通じて請負実績が認められる期間については、①②③の書類によらず請負の実績を算定できるものとします。
法人にあっては履歴事項全部証明書にある法人の目的により、必要年数に応じ、法人として建設業を営んでいると判断でき、かつ、年間を通じて請負実績が認められる期間については、①②③の書類によらず請負の実績を算定できるものとします。
なお、個人事業主の場合、法人の場合どちらであっても、登録の事実を確認できる書類(登録の通知書等)の提示が必要です。
⑵適正な社会保険に加入していること(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)
次のいずれにも該当する者であること。
健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。


<常勤であることの確認・証明書類>
1. 雇用保険に加入していることの確認資料
以下のいずれかの書類を提出することで、雇用保険への加入状況を確認する。
- 被保険者資格取得届の写し
- 雇用保険被保険者証の写し
- 雇用保険料の納付書または領収書の写し
2. 健康保険・厚生年金保険に加入していることの確認資料
以下のいずれかの書類を提出することで、健康保険および厚生年金保険への加入状況を確認する。
- 健康保険及び厚生年金保険の領収済通知書(写し)
- 保険料の納付書または領収書の写し
- 保険料の決済に係る計算書の写し
- 自社申告納付の場合:申告書控えの写し、または申告書に係る領収書・納付書・計算書の写し
※自社申請があった場合に限る
営業所技術者(専任技術者)
営業所技術者とは?
営業所技術者とは、建設業許可を取得・維持するために、営業所に常勤で配置することが義務付けられている技術者のことです。以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、令和6年の建設業法改正により、名称が変更されました。
営業所技術者の役割
営業所技術者は、営業所で請け負う建設工事に関する技術的な管理責任を担います。 その営業所に技術力が備わっていることを示す存在であり、発注者が安心して工事を依頼できる体制を整えるために必要です。
営業所ごとに下表のいずれかに該当する専任の技術者がいること
許可を受けようとする業種の工事について
・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
・学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の所定学科卒業後又は同法による専門職大学の前期課程の所定学科修了後3年以上の実務経験のある方
10年以上の実務経験を有する方
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方
(二級建築士、二級土木施工管理技士等)
<提出が必要なもの>
卒業証書の写し又は卒業証明書、実務経験証明書(様式第9号)、認定書の写し、監理技術者資格者証の写し、講習修了証の写し、監理技術者講習履歴 ※必要に応じて異なります。
許可を受けようとする業種の工事について
国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
※指定建設業については、イ又はハの規定で国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限る
<提出が必要なもの>
一般建設業許可の営業所技術者に必要な証明書に同じ+指導監督的実務経験証明書 ※必要に応じて異なります。